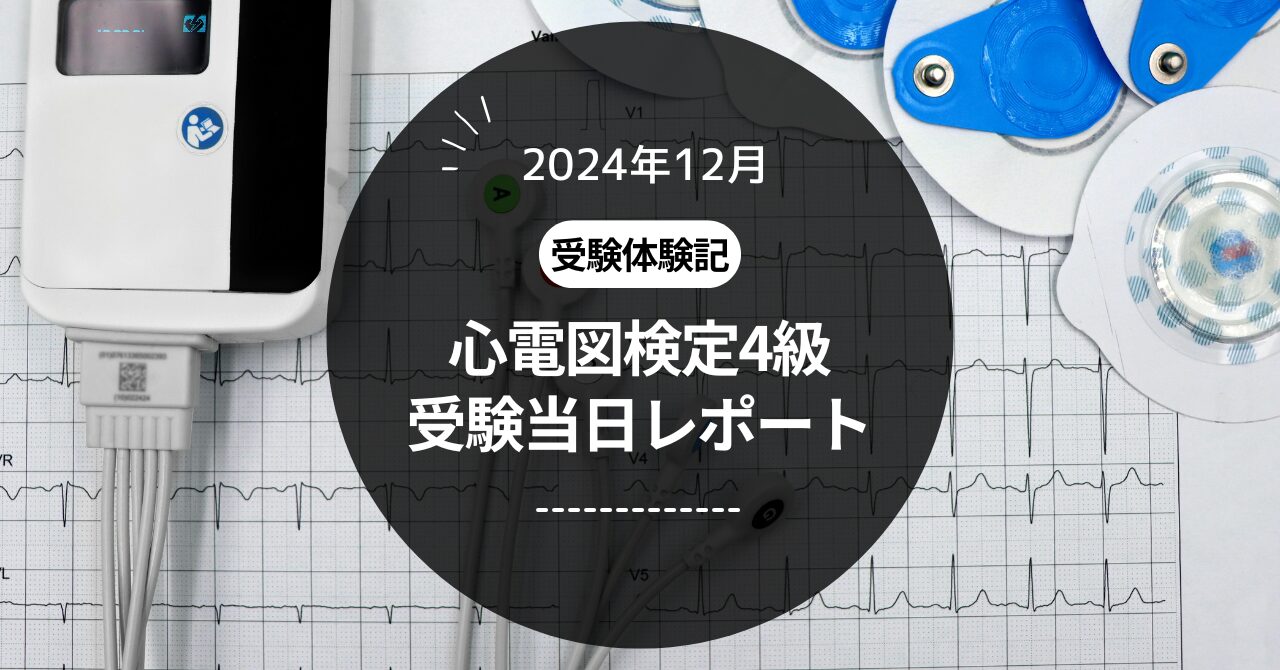先月、12月に実施された第10回(2024年度)心電図検定試験を受験してきました!
本記事では、当日の会場の様子、試験当日の流れをくわしく解説します。
- 心電図検定受験を控えている方
- 当日の様子が気になる方
心電図検定とは?

心電図検定とは、心電図を判読する技能が問われる試験です。日本不整脈心電学会が実施しています。
心電図検定最大の特徴は、医療系資格では珍しく誰でも受験ができることです。
医療資格を持っていなくても、心電図に興味のある人であれば受験できます。
過去には中学生や高校生が挑戦し、3級に合格されています。
わたしも医療職ではなく、医療資格も持っていない一般社会人ですが、受験することができました!
今回は、心電図検定4級を受験してきました。
受験当日の持ち物
実際に持っていったもの
受験当日、以下のものを持っていきました。
- 受検票
証明写真(縦3cm×横2.4cm)を2枚、貼り付けておく必要があります。
ちなみにこの写真サイズですが、履歴書用(縦4cm×横3cm)のものより小さい免許証用の大きさです。
履歴書の写真を使えばいいやと思っていたのですが、サイズが異なることに気がつき撮り直しに行きました……。
写真が貼られていないと受験できないので要注意です。事前に準備をしておきましょう! - 筆記用具
わたしは以下の4点を持っていきました。
テストはマークシート形式です。みなさんご自身が使用しやすいものを持っていきましょう。- シャープペンシル
- 鉛筆(HB)
- 消しゴム
- シャープペンシルの替え芯
- 腕時計
- マスク
- ディバイダー
一応持っていきましたが、自分の周囲で使用されている方は見かけませんでした。
4級レベルでは必要ないかもしれません。 - ファイル
心電図検定の受検票が届いたときに付属していたもので、受検票を入れておくために使用しました。当日同じようにファイルを持ってきている人が多かったです。
なかなか素敵なデザインのファイルで、これをいただけるだけでも受験するメリットがあったなと思います。
※心電図検定ファイルは10周年記念グッズのようです - 参考書
試験直前に見返すために以下の2冊を持っていきました。受付を済ませてから試験開始までかなり時間に余裕があったので、ぎりぎりまでこちらを読んでいました。
特に公式問題集については、試験会場で見返している方が多かったです。(もちろん試験中に見てはいけません)- 改訂3版 心電図検定2級/3級 公式問題集&ガイド
- これならわかる! 心電図の読み方 ~モニターから12誘導まで~ (ナースのための基礎BOOK)
持ち物(公式指定)
公式で持ち物として指定されているものは以下の通りとなります。必要に応じて持参しましょう。
- 受検票
- HBかBの鉛筆(シャープペンシル可)、消しゴム、鉛筆削り
- 腕時計(時刻表示機能だけのもの)
- マスク
【その他、試験中の使用を認めるもの】
- ディバイダーおよび定規
- ハンカチ、ポケットティッシュ、目薬
- メガネ、ルーペ(拡大鏡)
参考サイト:日本不整脈心電学会「実施要項・お申込み 第10回(2024年度)心電図検定試験」
※持ち物のなかには、事前に当日会場で許可を得る必要のあるものがございます。詳細は心電図検定公式サイト記載の実施要綱やお手持ちの受験票をご確認ください。
試験会場について

今回、わたしは大阪会場で受験いたしました。
場所は、グランフロント大阪 北館 地下2Fにあるコングレコンベンションセンター。
JR大阪駅の中央北口から、グランフロント大阪の北館までまっすぐに歩いていくとわかりやすいです。
当日はスタッフの方が地下へ降りるエスカレーター付近で誘導をされていました。(とてもありがたい!)
会場の室温
心電図検定の開催月は例年12月の真冬です。寒いと集中できないし、手がかじかんでしまうとうまく記入できない……。会場が寒くないか、とてもひやひやしていました。
結果、今回わたしの行った会場では空調がよく効いていて、暑いくらいでした。
「下着+ヒートテック+トップス+カーディガン」と厚着で会場に向かいましたが、それでは暑くなり、結局試験開始前にカーディガンは脱ぎました。
寒がりの方でも快適に受験できる暖かい会場だったと思います。
当日の会場では、完璧に防寒をした格好でなくてもよいでしょう(もちろん外を歩くときの防寒は忘れずに!)
お手洗い
私の行った会場には、個室数が多くきれいなお手洗いがありました。受験者数は非常に多かったのですが、その割にはお手洗いが混雑している印象はありませんでした。
開場してから試験開始まで40分ほどあったため、早めに会場に着いていれば、時間には余裕があるのでお手洗いも安心だと思います。
試験開始前の本人確認(受験受付)の際に、試験官の方から「お手洗いを事前に済ませておいてください」と念を押されました。また試験中に離席はできないとのアナウンスがありました。
必ず試験前にお手洗いは済ませるようにしましょう。
受験者層
試験会場がとても広くて驚きました! 同じ試験会場におおよそ600人受験者の方がいらっしゃいました。体感ですが、7割強が女性でした。
試験会場ではお知り合い同士だと思われる方々でお話しされているところも見かけたので、知人と一緒に受験している方もおられるようでした。
当日の流れ

ここからは試験当日の流れを振り返りたいと思います。
会場到着・受付
今回の試験開始時刻は10時40分。試験の受付開始時刻が10時で、試験開始時刻の40分前でした。
受付開始前の来場はご遠慮くださいと案内があったため、私は10時過ぎぐらいに到着するよう会場へ向かいました。
10時過ぎに会場に到着。
受付を開始してすぐだったからか、かなり人がいました。
混雑はしていましたが、スタッフさんにより整列され、大きな混乱はなく会場に辿り着くことができました。
人混みが気になる方は時間をずらして来場するとよいでしょう。
会場に着いたら、まずは自分の試験番号を確認して試験番号が書かれた席へ向かいます。
会場では複数の試験官の方が巡回しており、各自の席で受付を行っていました。
着席をすると、試験官の方が来られてそのまま受付をしていただきました。
受付後~試験開始前
受付後は、試験が始まるまで自由に過ごせました。
周囲は、参考書を読み返している人、スマートフォンを見ている人などさまざまでした。
試験開始~試験終了
試験開始時刻になると、まず受験の際の注意事項が説明されました。
そのあと問題用紙と回答用紙が配られ、名前を記入する時間が設けられました。
そして11時ちょうどに試験が開始。
試験時間は1時間です。
12時に試験が終了。
そのあと試験監督さんによる問題用紙・回答用紙の回収作業、確認作業等が行われました。
10分程度かかっていたと思います。
最後に試験結果の通知は2025年2月ごろであるとアナウンスがあり、試験が終わりました。
人数が多いため、試験番号ごとに順次解散となる規制退場でした。
さいごに
ここまで、当日の会場の様子、試験当日の流れを解説してきました。
受験当日というものは、とても緊張しますよね。私もとても緊張しているなかで試験に挑みました。
この記事から、皆さんに試験当日の情報を知っていただくことで、受験の不安を少しでも軽減できればと思います。
最後まで読んでいただきありがとうございました。